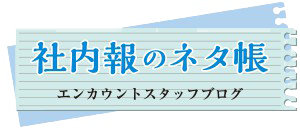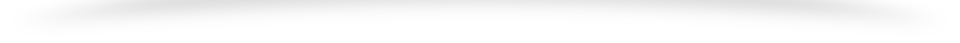社内報のための企画案を決める編集会議の場で、時間ばかりかかる割には編集委員から良い案がなかなか出てこないことにストレスを感じていませんか。結果として、いつも同じ企画の焼き回しばかりで誌面がマンネリ化してしまっては、編集会議を開催する意味がありません。忙しい業務の合間に、編集委員に集まっていただくからには、充実した会議にしたいですよね。実のある会議ができれば、企画の精度も、編集委員の連携もぐっと良くなります。
今回は、編集会議をより有意義にするための3つのポイントを紹介します。
1 事前準備と雰囲気づくりで意見が出やすい土壌をつくる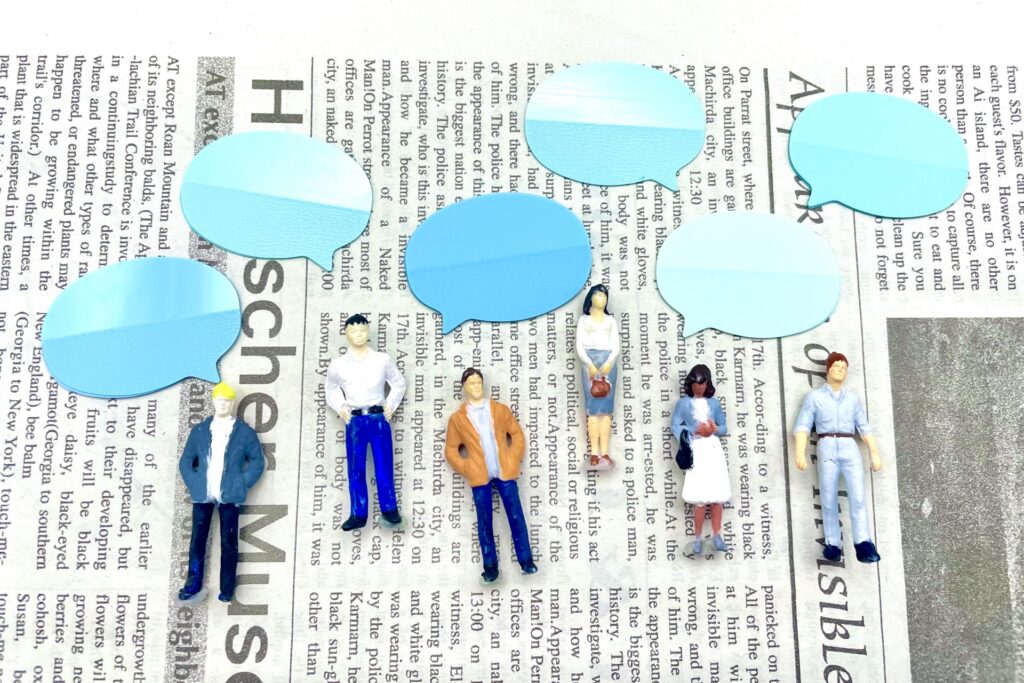
有意義な会議のためには、事前の下準備も大切です。各編集委員に、会議に向けて企画案を考えてもらうよう依頼をかけましょう。
・「企画案を5案考えてきてください」など、各編集委員に事前に依頼しておく
・過去の社内報など参考になる情報は共有しておく
全員が企画案を持ち、情報を共有した上で、会議に臨むことが有意義な会議にするための大前提となります。それでも、なかなか意見が出てこない場合は、以下のような背景があるかもしれません。
・自分の発言を否定されるのが怖い
・どんな企画がいい企画なのか分からない
・会議の雰囲気が堅くて発言しづらい
そんなときは、ファシリテーターとして発言しやすい雰囲気づくりに努めましょう。
例えば…
・本題に入る前のアイスブレイクとして近況を一言ずつ話してもらう
・「前号で反響のあった企画」など、比較的話しやすいネタから話す
・会議の冒頭は編集委員歴が長い人から順に意見を出してもらう
・全員の意見を尊重し、否定せず受け止める姿勢を見せる
それぞれから言葉が出始めると、空気が一気にやわらかくなります。編集会議の成否は「意見が出るかどうか」で8割決まると言っても過言ではありません。事前の下準備と当日の雰囲気づくりで会議を成功へ導きましょう。
2 読者の「顔」を思い浮かべる問いかけを

「どちらでもいい」「どうしよう」と、議論が停滞する会議には共通点があります。それは「誰のための企画か」が曖昧なこと。「読者のために」と言いつつ、読者=社員の前提を忘れ、自分たちの満足だけで企画を進めてしまっていませんか。
そんなときに効果的なのが「〇〇さんだったらどう思う?」という問いかけです。「新入社員のAさんがこの特集を読んでみたいか」「パートスタッフのBさんに知ってほしい情報は何か」など、顔が見える誰かを具体的な読者として設定し、その人になりきって考えることで議論にリアルな解像度が生まれます。
そしてもうひとつ有効なのが、言葉で話すだけでなく、出た意見を見える化すること。ホワイトボードに書き出したり、議事メモを画面共有すると考えが整理され、同じゴールに向かって進みやすくなります。決定項目や今後の課題など、目に見える形にして議論を進めていきましょう。
3 「発表の場」ではなく「決める場」にする
編集会議で陥りやすいのが、発表して満足してしまうこと。あくまで「決めること」を中心に据えるのがポイントです。
例えば…
・次号の制作にあたって決めなければならない内容は?
(新しい企画案、連載企画の次号のテーマ、特集内容など)
・決まらなかった場合の対応やスケジュールは?
このような問いを事前に整理しておくだけで、会議の流れが明確になります。現場にとって一番つらいのは、いざ原稿収集の段階になっても、誰が何をやればいいのかが見えない状態です。決定事項と未決定事項をその場で書き出しておくと、振り返りや引き継ぎがしやすくなるので、編集委員の方の納得度も高まります。
また、時間内に決めきれなかったとしても、「この件はAさんが案を出し、その後スケジュールを調整する」などのアクションを明示しましょう。なんとなく流して終わらないようにすることが、会議を「決める場」にする第一歩です。
編集会議の空気は、そのまま誌面の雰囲気にあらわれます。「何も決まらない」「みんな受け身」「とりあえず前回と同じで」、そんな会議が続いていたら、編集会議の在り方を見直すいい機会かもしれません。有意義な会議で、より良い社内報を目指しましょう。
<関連記事>
 <ディレクター:栗本>
<ディレクター:栗本>
今年も甲子園が開幕しましたね。高3の長男は1カ月ほど前に野球部を引退し受験勉強へ。私はすっかり高校野球ロス。この10年、土日は野球の予定が優先で、家族みんなが振り回され大変でしたが、青春時代を再び味わえたようでとても楽しい時間でした!!