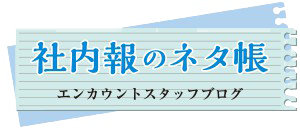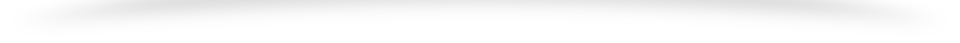社内報制作ご担当者の皆さま、こんにちは。
少し気の早いお話ですが、年始の社内報で恒例となっている社長の年頭所感は、単なる挨拶文でも儀礼的に掲載するものでもありません。社長の言葉を通じて「会社が何を大切にし、どこへ向かうのか」を社内で共有するための大事なメッセージです。しかし、どれだけ読者の記憶に残る誌面となっているでしょうか。毎年恒例の見慣れたページとなってはいませんか。
社内報は多くの人が始業前や休憩中、あるいはなんとなく手に取ったときに目を通します。情報を“求めて読む”というより、“そこにあったから読む”という動機の方が圧倒的に多いでしょう。だからこそ定型的な挨拶文では“スルーされやすい”ページになりがちです。言葉の重みや内容以前に「従業員たちはどんなときに読むのか」「読み終えた後に、どんな印象が残せるのか」という点から逆算して構成することが重要です。

読者の目線が立ち止まるポイントをつくる
印象に残らない理由の一つは、“毎年同じ配置や見た目になりがちで、かつ言葉が硬い”ということ。読者の脳が「しっかり読まなくても大体、何となくわかる」と判断してしまうのです。
それを打破するためには、誌面の中に「立ち止まるポイント」をつくることが大切です。デザインや配置などを変えていつもと違うリズムをつくり、読者の意識に引っかかりを生み出してみましょう。例えば、最初に目がつくからという理由で、冒頭のページに配置しがちですが、冒頭にはこれまでの取り組みや課題についての企画を入れ、年頭所感は中間部分に特集として持ってくるというように、流れを変えてみることも一つの手です。また、社長メッセージの最後に「この〇〇は、あなたの仕事にどう活かせますか?」と問いを立てたり、従業員目線のコメントを添えるなど、読み手が“自分ごと化”できるような工夫を加えると、ぐっと印象的にすることができます。
言葉が“残る”仕組みをつくる
内容で意識したいことは、メッセージが一方通行になっていないかどうかです。例えば、会社の今年度目標を語るときには「売上や利益」などの経営数字ばかりではなく、従業員が落とし込みやすいよう日々の業務に寄せたキーワードを盛り込むことで、距離が縮まります。
例えば「現場で〇〇の取り組みが増えていることをうれしく思う」という一文など、従業員たちにとって身近な活動を評価することで、読者は“見てくれているんだ”と感じ、自然と文章に引き込まれていきます。
義務感のもとで読む文章は、すぐに忘れられます。大事なのは「印象に残る」「あとから思い出す」構成にすることです。「このフレーズが心に残った」と感じさせる言葉を紡ぎ、レイアウトを工夫してみましょう。
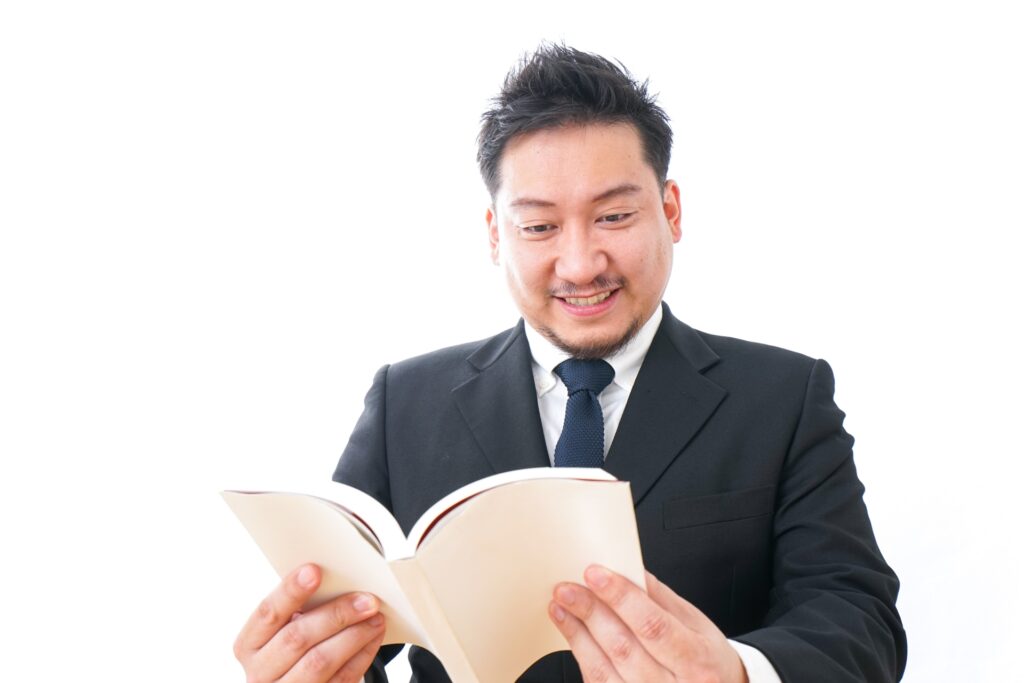
社長が時間を割いて綴った文章が従業員に届かないのでは意味がありません。担当者の皆さんのほんの少しの工夫で、社長のメッセージを読者にもっとしっかりと浸透させることができます。そしてその積み重ねが、社内報の存在価値をじわじわと押し上げていくのです。
次の年始号、社長の言葉が「読まれる言葉」に生まれ変わるよう、まずは土台から見直してみませんか。
【関連記事】
*************************
 <ディレクター:Y>
<ディレクター:Y>
暑い夏真っ只中でも、
来年に向けて動き出す季節はすぐきますね。