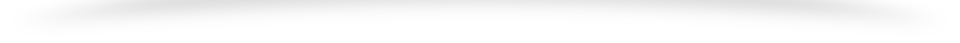社内報ご担当者の皆さんこんにちは。
部署や世代を超えて社員が交流し、普段なかなか聞けない本音を引き出すことができる座談会。テーマや対象者を柔軟に変えられるため、社内報の定番コンテンツとして幅広く活用されていますが、いざ構成する段階になると「どこまで整えるか」「どうすれば読者に響くのか」といった悩みに直面することも少なくありません。今回は、読者の心に届けるための座談会記事編集について紹介します。

会話のリズムを残して臨場感を演出
まず制作時に多くの担当者が悩むのは「言葉の調整」です。話し言葉をそのまま掲載すると冗長になり読みにくくなりますが、だからといって削りすぎてしまうと臨場感が失われがちです。そこで意識したいことは、”会話のリズムを意図的に残す”ことです。例えば、一人の社員が長めに語った発言に対して、別の社員が短い言葉で共感や反対の意を表す瞬間があります。端的に伝えるためその一言を削りたくなるかもしれませんが、温度感のある発言はあえて残すことでリアルさにつなげることができます。個々の発言を単なる情報のように羅列するのではなく、会話が交わされた”空気感そのもの”を読者に届けるという意識を取り入れることで、まるでその場に同席しているような没入感を演出できます。
言葉の奥にある価値観を引き出す
記事の価値を高める上で重要なのは「読者にどんな背景を見せられるか」です。発言者の体験談や意見を個人の話として単調にまとめるだけでは、記事の影響力は局所的になってしまいます。編集の視点を少し変えて「現場の情景」やそれが根差す「会社の文化・価値観」を意識的に引き出す工夫をしてみましょう。例えば、製造部の方を対象に「新たな製品制作の取り組み」をテーマとした座談会を開催した場合、“作業工程の苦労”を伝えるという視点ではなく、「高品質なものづくりを支えるプロ意識と誇り」として落とし込みます。一つのテーマでも視点を変えて取り上げることで個々の言葉に重みが加わり、会社全体の文化や価値観を引き立たせることができます。

記事を「未来の読者」へ届ける意識を持つ
社内報は発行して完結ではなく、会社の歴史や文化を伝える重要なアーカイブとして読み返されることもあります。そのため、今の読者だけではなく、数年後に初めてページを開く社員をも想定して「制作当時の空気が伝わる記事」になっているかということが鍵となります。
新しい制度について開かれた座談会であれば、導入時の社員が抱いていた「期待感や具体的な不安」が記録となり、プロジェクトを振り返る記事であれば、成功の裏側でメンバーが経験した「試行錯誤の過程や小さな失敗からの学び」を知る手がかりとなるのです。未来の社員が社内報を開いた時に、当時の社員の声の「温度」や「リアリティ」を感じられるような記事に仕上げる意識を持つことで、その場限りの座談会企画から“未来に残すべき貴重なドキュメント”へと変えることができます。
準備を整えて、ぜひ次回の座談会企画に役立てみてください!
<関連記事>
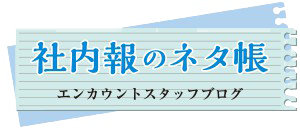

 <ディレクターY>
<ディレクターY>