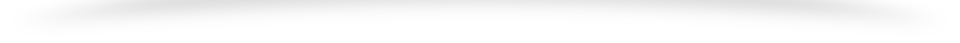社員に寄稿してもらった文章を、誌面にレイアウトする前に整理する時間をきちんと取っていますか。
忙しい社員に依頼した原稿は、多忙ゆえに細部まで文章が推敲されていないケースも多く、そのままでは読みづらい箇所や、意味のわかりにくい箇所が残っているかもしれません。
文章整理で大切なのは、「てにをは」や誤字脱字を正すのはもちろん、その文で伝えるべき内容がきちんと伝わるように整えることにあります。今回は読者が「読んでもよくわからない…」とモヤモヤさせないための、文章整理の方法を紹介します。
一般的でない言葉・専門的な言葉には注釈を入れる

たとえば、役員紹介の記事中で座右の銘を紹介する箇所があり、1人の役員が「縁尋機妙 多逢聖因(えんじんきみょう たほうしょういん)」という言葉を挙げたとします。経営者の好きな言葉として挙げられることが多い言葉ではありますが、日常的に使われるものではないので、初めて知った方も多いのではないでしょうか。
これは、昭和の政財界と深い関わりを持った陽明学者の安岡正篤(やすおか・まさひろ)による言葉とされ「良い縁が良い縁を呼んでいく様子は本当に不思議なもので、いい人に交わっているといい結果に恵まれる」ということを意味します。こうした一般的に知られていない言葉には、必ず注釈を付けしましょう。特に、例で挙げたような上層部の考え方につながる言葉であれば、なおさら意味を正確に伝える必要があります。
普段使わない漢字はひらがなに、文章向きの熟語は簡単な言葉に
「甚(はなは)だ」「些(いささ)か」「忽(たちま)ち」など、多くの人が一目見て読めない漢字を使用すると、読者は「何と読むんだろう?」と迷い、文章の途中で読むことを中断してしまいます。同じく「漸次(だんだんと)」「齟齬(食い違い)」といった、読み方を知らない人の多い漢字も、カッコ内のような簡単な言葉に置き換えた方が多くの人にとってわかりやすくなります。
社内報はあくまでコミュニケーションツール。社長メッセージなど格調高さを重視する文章でない限り「読者が理解しやすいかどうか」を基準にして手を入れましょう。
モヤモヤの原因「係り受け」のねじれは正す

「先月、とてもおしゃれな六本木のレストランに行ってきました。」
この文章には「とてもおしゃれ」なのが「六本木」なのか「レストラン」なのかがはっきりしない、という問題があります。どちらの意図で書かれているのかがわからないと、読者がモヤモヤを抱える原因に。「レストラン」がおしゃれだという意味の場合は、以下のようにリライトしましょう。
「先月、六本木にできた、とてもおしゃれなレストランに行ってきました。」
この文では「おしゃれな」が修飾語で「レストラン」が被修飾語となり、係り受け(文の中で語句どうしの意味がつながること)になっています。係り受けには他にもいくつかルールがありますが、ここでは例文のように「修飾語と被修飾語はできるだけ近づける」ことを覚えておきましょう。
珍しい読み方・漢字の名前には必ず読みがなを
①「忽那」
②「蒔田」
③「上遠野」
これらは「初見では名前が読めない芸能人の名前」に関する、あるランキングで上位に入った方々の苗字です。みなさんは読めますか?
正解は以下のとおり。
①くつな
②まきた(もしくは「まいた」)
③かとおの
芸能人であれば名前を読めなくても日常生活で困ることはありませんが、社内報に載っている人の名前を読めなければ「難しい名前の人」としか認識できず、その後のコミュニケーションに障害が発生しかねません。あまり見かけない名前や、自分が初読で読めなかった漢字の名前には読みがなをつけましょう。
また文章を整理する際には、寄稿者に断りを入れ、許可を取ることを忘れないようにしてください。読者が読みやすく正確に情報が伝わる文章になるよう、心を砕いて行いましょう!
〈関連記事〉
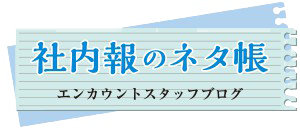

 ディレクター:今枝
ディレクター:今枝