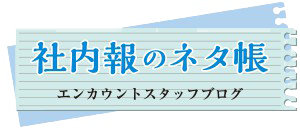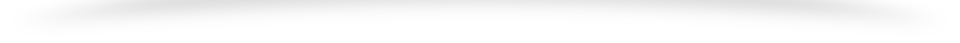「せっかく作っているのに、あまり読まれていない気がする」
「毎号マンネリ化している」
「担当者の負担ばかり大きい」
社内報の制作を続けるなかで、このような声を聞くことがあります。長年続けている社内報には積み重ねの価値がある一方で、知らず知らずのうちに「どんな意図で発行しているのか」「誰に向けたものか」があいまいになっている場合も少なくありません。
こうした課題を整理し、目的や読者像を改めて明確にすることで、訴求力のある社内報へとリニューアルすることができます。
今回は、社内報のリニューアルを考える際にポイントとなる5つの視点をご紹介します。

1 発行目的や編集方針にブレがないか?
社内報を発行する上で最も大切なのは、「何のために発行するのか」という目的です。社員のエンゲージメント向上、経営方針の浸透、職場の一体感づくりなど、目的は会社ごとに異なりますが、ここが明確でないと記事のトーンやテーマが散漫になり、結局、何を伝えたいのかが分からない社内報になってしまいます。
リニューアルの際には、発行の目的や目指す姿を改めて言語化し、編集チーム全体で共有することが重要です。これにより、記事の方向性や内容の選定にブレが生じず、社内報全体の一貫性を保つことができます。編集方針が転換される場合は、タイトルや表紙から見直すことも検討しましょう。
2 読まれる企画内容になっているか?
社内報が読まれない理由に「内容が身近でない」「自分ごとに感じられない」といった声が聞かれます。新入社員とベテラン社員、工場勤務と本社勤務でも関心は違います。読者層が幅広いからこそ、各企画の意図と伝えたい相手を明確にすることが大切です。一方で、福利厚生制度など多くの社員に共通する情報も盛り込みましょう。「現場社員の工夫や挑戦」「社内イベントの裏側」など、人にフォーカスした企画もおすすめです。
また、重要な内容は巻頭などで目立つように、箸休め的な企画は中間のページにするなど、硬いテーマと柔らかい企画をバランスよく配置し、ページをめくりたくなる台割を意識しましょう。リニューアルのタイミングで読者アンケートやヒアリングを行い「どんな記事が楽しみか」「読みやすいページはどこか」といった声を反映すれば、より一人ひとりに寄り添った社内報へと近づきます。
3 魅力的なデザインか?
「文字量が多過ぎて圧迫感がある」「写真のトーンが統一されていない」「色使いがバラバラ」「デザインが古くさい」そんな誌面になっていませんか。
どれだけ内容が充実していても、目を惹くデザインや、読みやすい文字組みでなければ、最後まで読んでもらうことはできません。創刊時から長年固定化されているフォーマットのデザインなども、リニューアルの際に見直しましょう。
4 発行頻度やボリュームは適切か?
「毎月の発行で担当者の負担が大きい」「年1回では情報が古くなり間延びしてしまう」といった悩みもよく聞かれます。
発行頻度や誌面ボリュームを検討する際は、社内のニュースサイクルと制作体制の両面から考えることがポイントです。人事異動や社内イベントが多い会社なら隔月刊、落ち着いた業種なら季刊など、適切な発行サイクルについて検討しましょう。発行回数を減らす場合も、1号あたりのページ数を増やすことで情報量を確保し、社員に必要な情報を届けることが大切です。
5 制作体制が適切か?
どんなに内容が良くても、制作体制が整っていなければ発行を続けることが困難になってしまいます。
社内で編集を担う人材は足りているか? 写真やデザインは誰が担当するのか? 外部パートナーをどのように活用するか?こうした体制を現実的に見直すことで、継続可能な仕組みが整います。特にリニューアル時は、編集会議や校正フローなども改めて整理し「属人的にならない体制づくり」を意識することが重要です。
リニューアルは、単にデザインなどの見た目を変えるだけではなく、社内報の価値そのものを見直す絶好の機会です。社内報は企業文化を映す鏡。リニューアルを通じて、会社にとっても社員にとっても有意義な社内報を実現していきましょう。
【関連記事】
実際どうなの!? 社内報リニューアル成功事例 – 社内報のネタ帳

<ディレクター栗本>ようやく秋の訪れを感じられるようになりました。秋一のお楽しみは、くりきんとん! 素朴な甘さがたまりません。コーヒーにも緑茶にも合う、万能スイーツですね。