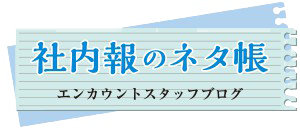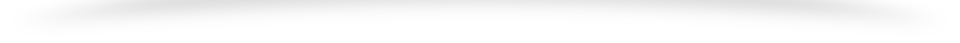社内報ご制作担当者の皆さま、こんにちは。
社内報には方針発表や制度改定、DX促進など、読者にとって一見すると“とっつきにくく、理解し難しい”テーマがしばしば登場します。制作担当者は「堅すぎると読まれない」「どうすれば理解してもらえるか」と悩みがちですが、実は少し工夫を加えるだけで読者の読もうとするモチベーションを高めることができます。今回は、難解なテーマを読まれる記事に変えるための3つの工夫を紹介します。
1.入り口で読むハードルを低くする
読むかどうかを動機づける重要な要素のひとつは「見出し」です。ただ記事の内容を説明しただけの見出しでは、読者は身構えてしまうかもしれません。そこで効果的なのが「こんな疑問を持つ人も多いのでは?」という、読者が読んでいてつまずくであろう「分かりにくさ」を想像し、分かりやすく心に響く言葉に置き換えて伝えること。そうすることで単なる説明・紹介記事から、読者が抱いている疑問を一緒に解決していくストーリーへと変わります。
社内報では記事の正確さと同じくらい、“入りやすさ”も重要なポイントになります。入り口を読者目線に立った言葉や表現に置き換えてハードルを下げることで、関心の角度をグッと上げることができます。
2.あれもこれもとつめこまない
難しいテーマほど、あれもこれもとつめこんでしまい、原稿がボリュームオーバーになりがちです。しかし、情報量が多すぎると読者の理解がぼやけ、肝心な部分が頭に残りません。大切なことは、要点を一つに絞って伝えることです。
また、すべてを一度に解説しようとせず、あえて“余白”を残す構成を意識してみましょう。ここでいう余白とは、誌面デザインのスペースのことではなく「読んだ後に会話や議論が生む余地」のことです。例えば2号にわたって掲載する、テーマに対する現場の声を募集するなど、読者が自分なりに考えたり、周囲と話し合ったりできるような構成にすると、理解が深まり、読後の効果がぐっと高まります。

3.小学生でも理解できる表現にチェンジ
専門用語が多いほど、読者の理解度は低くなるもの。聞き慣れない難語を羅列してしまうと、具体的なイメージが浮かばず言葉が頭に入ってこない人もいます。脳が拒否反応を起こさないようにするためには、時には小学生でも分かるような表現に“砕く”というテクニックを使いましょう。制作者の皆さん自身が、肩の力を抜いてすらすらと読めるというレベルで書いてみてください。
難しいテーマを読みやすくする秘訣は、単に情報を削るだけではありません。入り口を入りやすくする、要点を絞る、イメージしやすい言葉遣いや表現に“砕く”などの工夫をすることで、読者に届くメッセージへと変わります。社内報は説明書ではなく、社内コミュニケーションや行動のきっかけを生むためのものです。どうすれば拒否感なくスムーズに読んでもらえるか、伝えたいことがしっかり伝わるかを考え、工夫をすることで、読者との距離が近づきます。
 <ディレクターY>
<ディレクターY>
知識や経験に由来した思い込みを捨てて、
ゼロベース思考で物事をみることも時には必要ですね。