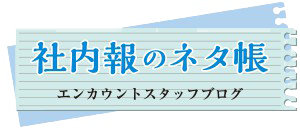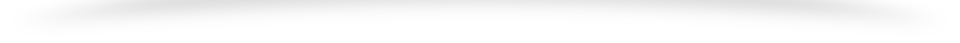社内報の制作には、文章作成は欠かせません。しかし「文章作成」というと、つい難しく考えてしまいがちです。たとえば「5W1Hを全部入れなければいけない」「起承転結でまとめないと読んでもらえない」など、ハードルを高く設定してしまう人も多いのではないでしょうか。でも実際には、文章の基本はもっとシンプルです。まずは「誰に、なにを、どう伝えるか」を意識するだけで、読者に伝わる文章に近づけることができます。これは広告やマーケティングで基本とされる考え方ですが、社内報の文章づくりにも共通する考え方です。
誰に――読者をイメージする
たとえば「新入社員に読んでほしい記事」を作るなら、専門用語をなるべく避け、入社1年目でも理解できる言葉選びが大切です。「ベテラン社員にもじっくり読んでもらいたい記事」なら、現場での具体的な課題や数字を交えた説明など、深みのある情報を加える必要があります。社内報の場合、「ターゲット=全社員」と思いがちですが、特定の読者を意識することで内容に芯が生まれ、文章が自然と引き締まります。

なにを――伝えたいことをなるべく絞る
文章作成が苦手な人こそ、記事の中にはたくさん情報を詰め込みがちですが、記事のメッセージはなるべく絞ることをおすすめします。例えば「福利厚生制度を紹介したい」とき、制度の概要も利用手順も利用者の声も、あれもこれも均等に盛り込もうとすると、記事全体の印象がぼやけてしまいます。
「まずは制度の魅力を知ってほしい」のか、「実際の利用シーンをイメージしてほしい」のか。一番伝えたいことを重点的に書き、それ以外はサブ的に扱うなど、優先順位をはっきりさせると文章の意図がクリアになり、読みやすくなります。

どう――伝え方を工夫する
そして最後は「どう伝えるか」です。同じ内容でも、インタビュー形式にするか、ストーリー仕立てにするか、写真中心の構成にするか、で、読者の受け止め方は大きく変わります。
たとえば「新入社員研修のレポート」を記事にする場合、
・研修スケジュールを淡々と並べると、どんな研修を受けたのかの流れは伝わるけれど味気ない
・研修を受けた新入社員の感想を中心にまとめれば、研修内容の詳細は伝わりにくいが“等身大の声”として読者の共感を得やすい
といった違いが生まれます。
社内報では「読みやすさ」と「共感しやすさ」がカギです。堅い説明口調をやわらげて会話調にしてみたり、社員の生の声をのせたりすることで、親しみやすさがぐっと増します。

社内報は大切なメディア
社内報は、社員同士の理解や共感を深めるための大切なメディアです。だからこそ、文章作成の基本を意識して丁寧に伝える工夫が重要です。
「誰に、なにを、どう伝えるか」。シンプルですが、この問いを意識して文章を作成することで、社内報の記事は今よりもっと伝わる、もっと読まれるものに変わっていくはずです。
【関連記事】
<執筆者:仲山>
 「誰に、なにを、どう伝えるか」。広告やマーケティングの基本として、広告代理店に在籍していた時に教わった考え方です。文章づくり全般にも通じる普遍的なライティングの考え方だと思います。
「誰に、なにを、どう伝えるか」。広告やマーケティングの基本として、広告代理店に在籍していた時に教わった考え方です。文章づくり全般にも通じる普遍的なライティングの考え方だと思います。